
みかん選びで失敗した経験はありませんか?
冬の果物といえば、やっぱりみかん。手軽に食べられて、こたつのお供にも欠かせませんよね。
でも、同じ売り場で同じ値段で買ったのに、「思ったより酸っぱかった…」「味が薄い…」とがっかりしたことはありませんか?
実は、甘いみかんを選ぶにはちょっとしたコツがあります。プロの目線で売り場に立っていると、「この人は良いのを選んだな」とわかる瞬間があるんです。
今回は、青果担当として日々みかんを扱う立場から「甘いみかんを選ぶ3つのコツ」をお伝えします。
実は皮の見た目が最重要ポイント
多くの人が「色」や「ツヤ」でみかんを選びますが、本当に大事なのは 皮の表面の見た目 です。
甘いみかんは、皮の表面がぼこぼことしていて、まるで「ブロック状」に区切られているように見えます。
これは成長過程で「水分ストレス」がかかることで起こります。水分が不足すると皮の成長が抑えられ、表面がデコボコになり、その分糖分が果肉に凝縮されるんです。
つまり、見た目が「きれいでつるんとしたみかん」よりも、少しゴツゴツしているみかんの方が甘い可能性が高いのです。
実際、現場でもお客さんに「どうやって選んだらいい?」と聞かれたときは、このポイントを一番最初にお伝えします。
甘いみかんを見分けるその他のポイント
1. 皮の薄さとハリ
皮が厚くてブカブカしていると、果肉と皮の間にすき間ができてしまい、水っぽくて味が薄く感じます。
逆に、皮が薄くてピタッと果肉に張り付いているものはジューシーで味が濃い傾向があります。
2. ヘタの小ささと色
ヘタは栄養や水分が通る大事な部分。
ヘタが小さくて緑色が濃いみかんは、水分の行き過ぎが抑えられ、糖度が上がりやすいんです。
3. 小玉サイズを選ぶ
「大きい方がお得」と思って選ぶ人も多いですが、実は小玉サイズの方が甘いことが多いです。
小さい実ほど栄養が凝縮されるので、味が濃くなりやすいんですね。
糖度センサーで選果されたブランドみかんも狙い目
最近は、農協やブランド産地で 糖度センサー を使って選果するケースが増えています。
糖度センサーとは、果実に光を当てて内部の糖度を測定する機械。
人の目では分からない部分を判別できるので、出荷される段階で「糖度の基準」を満たしたみかんだけが市場に出ます。
有名ブランドのみかん(例:有田みかん、愛媛のみかんなど)は、この仕組みを取り入れていることが多く、平均的に糖度が高く安定した味が楽しめます。
こうしたブランド品は価格は少し高めですが、ハズレが少ないため一度好みの味に出会えればリピート率が高いのも特徴です。
よくある勘違い
- 「ツヤがある=甘い」
→ 実は関係ありません。表面の水分やワックスでツヤが出ているだけの場合もあります。 - 「重い=甘い」
→ 確かに重さは水分量の目安になりますが、糖度の高さとは必ずしも一致しません。
青果担当からの裏話
同じ農家から届いたみかんでも、1箱の中には糖度の高いものと低いものが混じっています。
お店によっては「熟して甘いものを手前に」「まだ若いものを奥に」と配置する工夫をしていることもあります。
実際に売り場で働いていると、お客さんから「どうやって選んだらいいの?」と聞かれることがよくあります。
以前アドバイスした方が後日また来店されて、「教えてもらった通りに選んだら当たりだった!」「家族にも喜ばれました」と感想を伝えてくれることもあり、こちらもとても嬉しくなります。
こうしたやり取りは、販売現場ならではのやりがいのひとつです。
また、同じ産地・同じブランドのみかんでも、収穫のタイミングや気候条件によって味に差が出ることもあります。
だからこそ、迷ったときにはぜひその売り場の担当者に直接聞いてみるのがおすすめです。
親切に答えてくれる担当者がいるお店は、そもそも仕入れ段階から選定基準にこだわっているケースが多く、結果的に取り扱う商品全体の品質が安定しています。
これは「良いお店を見極めるポイント」にもなります。
まとめ:今日から使える甘いみかんの見分け方
甘いみかんを選ぶときは、このポイントを押さえてみてください。
- 皮の表面がぼこぼこしてブロック状に見えるもの(糖分凝縮のサイン!)
- 皮が薄くてハリがある
- ヘタが小さく緑が濃い
- 小玉サイズを選ぶ
- ブランド産地や糖度センサー選果済みのみかんを選ぶ
- 担当者に聞いてみる(親切に答えてくれるお店は仕入れにこだわりあり)
この6つを意識すれば、みかん選びでの失敗はぐんと減り、美味しいみかんに出会える確率が高まります。
ぜひ次のお買い物で試してみてくださいね。


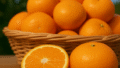
コメント