
みかんの味が変わるのは季節のせい?
秋から冬にかけて、スーパーのみかん売り場を見ると、「極早生(ごくわせ)」「早生(わせ)」「青島」など、時期によって表示が変わっていきますよね。
「どれを買えば甘いの?」「時期によってどう違うの?」と迷う方も多いと思います。
実はこの表示は、収穫時期の違い=味わいの違いを示しています。
青果担当として毎年みかんを扱ってきた立場から、それぞれの特徴とおすすめの食べ方をご紹介します。
みかんの主な出荷時期の流れ
日本のみかんのシーズンはおおむね 9月〜3月ごろ。
早い時期の「極早生」から始まり、晩冬の「青島」まで、段階的にリレーのように旬が移っていきます。
| 品種区分 | 出回り時期 | 特徴 |
|---|---|---|
| 極早生(ごくわせ) | 9月下旬〜10月下旬 | さっぱり爽やか。酸味がやや強いが、初物の香りが魅力。 |
| 早生(わせ) | 11月上旬〜12月上旬 | 酸味と甘みのバランスが良い。徐々に甘みが増してくる。 |
| 普通温州(おんしゅう) | 12月中旬〜1月 | 甘みが強く、果汁もたっぷり。味が安定する時期。 |
| 青島(あおしま) | 1月〜3月 | コクがあり、しっかりした甘さ。貯蔵熟成で味が深まる。 |
💡 ポイント:季節が進むほど、酸味が減って甘みが増す傾向があります。
極早生みかん|秋のはじまりを告げる爽やかな味わい
まだ気温が高い時期に出回る、最初の温州みかん。
皮がやや緑がかっており、酸味が強めですが、シャキッとした爽やかさが特徴です。
「まだ酸っぱそう」と思われがちですが、冷やして食べるとバランスが良く、秋の初物として根強い人気があります。
早生みかん|甘みと酸味のバランスが絶妙
11月ごろから本格的に出回り始めるのが早生みかん。
皮が薄くてむきやすく、果汁が多く、甘みと酸味のバランスがちょうど良いタイプです。
この時期のみかんは、**「家族みんなで食べやすい味」**として最も人気があります。
産地によっては糖度センサー選果も導入され、甘さが安定している商品が増えています。
普通温州みかん|冬本番の味わい
12月中旬〜1月ごろに出回る一般的な温州みかん。
この時期になると酸味が落ち着き、濃厚な甘みとジューシーさが特徴になります。
特に寒い日が続くと、みかんの糖度がさらに上がる傾向があります。
保存にも向いており、常温でも2週間ほどは美味しさをキープできます。
青島みかん|貯蔵で甘みが増す“完熟系”
1月以降に多く出回るのが「青島みかん」。
皮がやや厚めで日持ちがよく、貯蔵熟成によって甘みとコクが増すのが特徴です。
貯蔵中に酸味が抜け、味がまろやかになるため、年明け以降のみかんは「濃い甘さ」が好きな方にぴったりです。
同じ青島でも、貯蔵期間によって味が微妙に変化するのも楽しみのひとつ。
青果担当のおすすめの楽しみ方
実際の売り場では、季節が進むごとに味わいが少しずつ変化していくのがよくわかります。
例えば、極早生の頃は「さっぱり」、早生は「ほどよい甘さ」、青島は「濃厚」。
この変化を意識して食べ比べてみるのも面白いですよ。
また、同じ産地・同じブランドでも、年によって味の傾向が変わることがあります。
「今年の○○みかんは甘いね」と感じたら、それも自然の恵みの表れです。
まとめ:みかんの時期ごとの味を楽しもう
- 極早生(9〜10月):爽やかで酸味のある初物
- 早生(11〜12月):甘みと酸味のバランスが良い
- 普通温州(12〜1月):濃厚でジューシー
- 青島(1〜3月):貯蔵でコクが増す完熟系
みかんは時期が進むごとに味が変化する果物。
お気に入りの味を見つけて、旬の移ろいを楽しんでみてください。


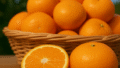

コメント